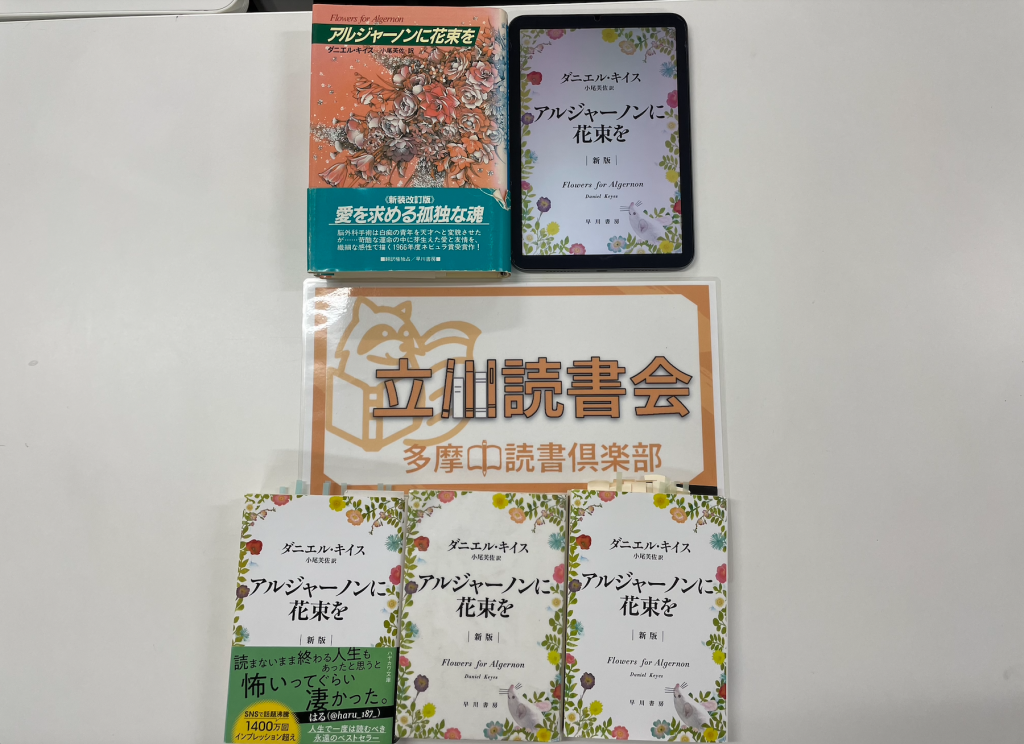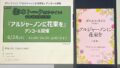📚6/15に立川読書会、「課題本『アルジャーノンに花束を』読書会」の感想レポートです。
※本編のネタバレを含みます
本記事は読書会ででた意見を再構成・加筆編集してます。
1. 読後の第一印象
• チャーリーの変化に共感と悲しみ
チャーリーが知的に急成長し、その後再び衰退していく過程に大きな感情の揺さぶりを受けた。
→ 「幸せとは何か」「知ることは善なのか悪なのか」といった問いに繋がっていく。
• 笑われていた過去と、“擬似的な愛情”?
知能が低かった頃、チャーリーは周囲からのからかいやいじめにもかかわらず、愛されていたと感じていた。しかしそれが「欺かれていた」と知ったときの衝撃が語られる。
2. 知能と幸福、そして“変化”の苦しさ
• チャーリーの苦悩の本質は“変化”にあった
頭が良い/悪いということより、急激に変化したことで感情が追いつかず、それが苦しさを生んだのではないかという分析。
→ 知能の高さや低さそのものが問題ではない。
• 知ることの“罪”とジレンマ
禁断の果実の喩えを使い、「知ることが苦しみを生む」テーマが語られる。
→ 知識欲と感情のバランス、幸福の関係性が議論される。
3. 人生のピークと下り坂の普遍性
• チャーリーの人生は圧縮された“人間の一生”
幼少期→成長→衰退という人生の流れを短期間で体験したチャーリーは、誰しもが歩む運命を象徴しているという意見。
• 老い・認知症との共通性
徐々に忘れていく、できていたことができなくなるという点で、認知症の進行との共通点が語られる。
4. 優生思想・障害・社会との関係
• “優れていること”とは何か?
障害をもつ人の生き方、社会の在り方、個性をどう受け止めるかといった根源的な問いが浮かび上がる。
→ 医療・制度・薬物治療と自己のあり方のジレンマ。
5. 幼少期体験・家族との関係
• 母親からの“呪い”と、記憶の重み
チャーリーの母親が「頭が良くなれ」と強く願ったことが、彼の人生に大きな影響を与えた。
→ それが愛情だったのか、支配だったのかを考える。
• “リトル・チャーリー”と無意識の影響
幼い頃の自分”リトル・チャーリー”(本田圭佑リスペクト)が今の自分を見ているという表現は、自己分裂と無意識の葛藤を象徴。
6. 知識と体験のギャップ(クオリア)
• メアリーの部屋の思考実験
「知識で知っていても、体験しないと本当には理解できない」
→ チャーリーも、知能で分かっていても、感情が追いつかないという苦しみを味わった。
7. 恋愛と“愛”の違い、アリスとキニアン先生の対比
• アリスとの関係は恋、“キニアン先生”は愛
変わってしまったチャーリーを受け入れるかどうかの違いが、「一時的な感情(恋)」と「継続的な愛情(愛)」の違いとして描かれていた。
• “変化する相手”とどう向き合うか
パートナーが変わってしまったら?という問いが投げられ、受け入れることの難しさが語られた。
8. 文体と翻訳の巧みさ
• チャーリーの文章の“変化”が物語の大きな要素
初期のたどたどしい文から、次第に知的な文に変わり、また崩れていく。その変化が読者に強い印象を与える。
• 翻訳の工夫と工芸性
訳者あとがきより、誤字や文法ミスを文字表現で再現した苦労が語られ、オーディオブックとの違いも比較された。
9. 作者についてと、物語の力
• ダニエル・キイスの経歴と“医学的リアリティ”
著者ダニエル・キイスが医者志望だった背景や、ビリー・ミリガンを描いたことなどから、心理描写や医療描写の深さが際立つ。
• ハッピーエンド?“受容としての救い”
物語は単なるハッピーエンドではない。が、“受け入れる”ことでの静かな救いが描かれているという解釈が多かった。
10. 対話を通しての感想
• 自分の中の“悪癖”や“呪い”との向き合い
過去の記憶や親からの言葉が、自分の行動を縛っているという認識。
→ 自分を苦しめている価値観を見直す必要性。
• 人間の複雑さと“受け入れ”の難しさ
登場人物が善悪では割り切れず、どこか共感できてしまう。
→ それがこの作品の深みであり、人間というものの真実を突いている。
まとめ
今回の読書会は、『アルジャーノンに花束を』という作品を通して、「知識・成長・変化・幸福・受容・愛」といった多角的なテーマを深く掘り下げる場になりました。皆さんが自分の体験や視点を持ち寄り、単なる感想の共有にとどまらず、「生きること」の意味に迫るような対話になっていたのが印象的でした。