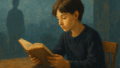読書は勉強の代わりになるのか?
結論から言うと、読書は非常に効果的な学びの手段だといえます。ではなぜそう言えるのか、科学的な研究や偉人の例から見ていきましょう。
読書は脳を深く使い、理解力や記憶力を高める
科学的な研究によると、読書は脳の中でも「言語」「記憶」「論理的思考」などさまざまな部分を活性化するとされています。
例えば、エモリー大学の研究によれば、小説を読むと、脳のつながり(特に物語を理解したり、人の気持ちを想像したりする部分)が一時的に強くなる。さらに、読後も数日間は体感的に意味を理解する脳の部分が変化し続ける(Berns et al., 2013)と示しています。
また、教育心理学では「精緻化リハーサル(elaborative rehearsal)」という学習法が重要とされています。これは、学んだことの意味を考え、自分の知識と結びつけながら理解する方法(Craik & Lockhart, 1972)です。ここで重要なのは、新しい情報を既存の知識と結びつけながら深く処理するのこと。つまり、単語をただ繰り返して覚える(維持リハーサル)だけではなく、その単語の意味や関連知識、自分の経験とリンクさせて覚えるということ。読書は単なる反復的な勉強より、むしろこのポイントを押さえているため、高い学習効果が期待できます。
福沢諭吉からデカルトまで ―― 本が育てる知恵
さて、過去の人々は読書をどのように考え実践していたのでしょう。
例えば、日本の近代化に大きく貢献した福澤諭吉は、まさに読書によって身を立てた人物でした。
彼は、もともと貧しい中津藩の下級武士の家に生まれました。しかし幼い頃から本を読み、独学でオランダ語や英語を身につけました。
特に江戸に出てからは本格的に洋書の翻訳に挑み、そこから得た知識をもとに『学問のすゝめ』などを執筆。広く日本人に「学ぶこと」の重要性を説きました。
彼の思想は後の明治政府にも大きな影響を与え、日本の近代教育の礎となりました。彼の生き様は、読書が一人の人生だけでなく国の行末にも影響与えた好例といえます。
また哲学者デカルトは「良書を読むことは、過去の最も優れた人々と会話するようなものだ」と述べています。
このように、読書は歴史的な人物にも大きく影響を与えてきた営みだったのです。
読書は、学びにとって非常に効果的な手段
このように、脳科学的にも偉人の例から見ても、読書は深い理解と知識の定着を助ける良き学びの手段ということがわかりました。
勉強というと敷居が高いですが、読書はそれに代わって余りある方法だと思えば、より前向きに読書に向かえますね。
出典・参考文献
・Berns, G. S., Blaine, K., Prietula, M. J., & Pye, B. E. (2013). Short- and long-term effects of a novel on connectivity in the brain. Brain Connectivity, 3(6), 590–600.
・Craik, F. I. M., & Lockhart, R. S. (1972). Levels of processing: A framework for memory research. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 11(6), 671–684.