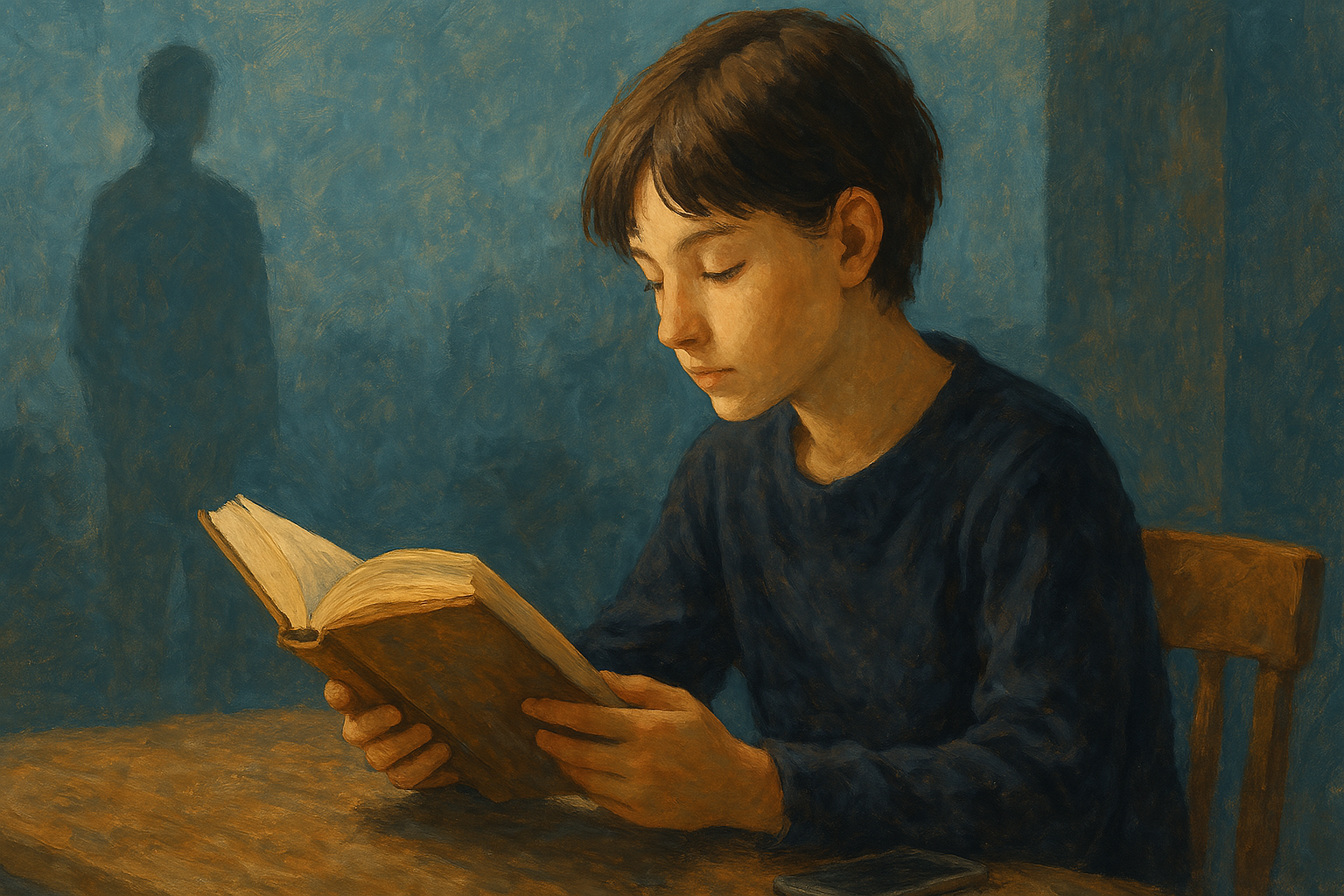小説の読み方なんて、誰も教えてくれなかった。
「小説って、ただ読めばいいだけじゃないの?」そう思ってページをめくれども、「面白かった」ということ以外何も残らない、ということは往々にしてあることです。
それもそのはず「小説の読み方」というものはわかっているようで、誰も教えてくれる機会などないからです。
国語の授業で教えられるのは、テストを解くための”読解術”であり、読書を深く楽しむための方法ではありません。
でも安心してください。小説の読み方には、ちゃんと“コツ”があります。科学・思想・文学をヒントに「心と頭を動かす読み方」をここに記したいと思います。
小説の読み方:実践的アプローチで心と頭を動かす方法
小説の真の読み方をズバリ簡潔に言うと「登場人物になりきり、問いを携え、気づいたことを言葉にする」と言うことです。これによって、ただ物語に流されるだけではなく、自分自身の感性や思考を刺激し、深い学びへとつながります。
それでは、具体的にどのようにすれば、この読書術を実践できるのでしょうか?すぐに試せるコツをいくつかご紹介します。
1. 登場人物の立場に立つ
登場人物の立場に立つことはあたりまえ、自然とできてる人も多いと思いますが、それは読書の入り口に過ぎません。さらなる深みへいたるには、もう一歩、二歩と踏み込む必要があります。
確かに物語を味わうには、まず自分が共感しやすい人物に移入してみることが必要です。
しかし多くの場合、小説は一人の登場人物で完結することはありません。例えば、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』には、イワン、アリョーシャ、ドミートリーといった様々なる立場のキャラクターが複雑に入り乱れています。
人は自分と近い考えの人物に自然と移入するものですが、それでは考えや感性の幅は広がりません。小説はあらゆる人物の内面や態度をなぞるフィールドなのです。それぞれの視点に立って「この人はどんな考えや態度で生活しているのか?」と想像しながら読む(時には読み返すことも必要となるでしょう)ことを重ねていくと、人間関係の立体的な構造が見えてくるのです。
このように、他人の立場になって物語を読むことは、脳内で“疑似体験”を引き起こします。心理学ではこれを「視点取得(perspective-taking)」と呼びます。これは単なる想像力の訓練にとどまらず、自分とは異なる価値観や感情を内側から理解しようとする知的・感情的プロセスです。こうした読書体験は、現実の複雑な人間関係の中でも共感力や判断力を高め、結果的に自分の考え方を深めるとともに、社会を多面的に捉える糧となります。
2. 感情や気づきをメモする
読みながら、ふと心に響いたセリフや印象的な場面をメモすることはあるでしょう。ただそこに留まることなく、自分が感じたこと、考えたことも同時にメモしてみてください。
読書中に浮かんだ感情や疑問を書き留めることは、文字を追う「読む」行為を、自分の頭を働かせて「考える」行為へと進化させるプロセスです。心理学では、思考を言語化することで情報処理が整理され、記憶の定着や理解が深まることが知られています。感情を記録することは、自分の価値観の輪郭も明確にすることになります。つまり、感じたことをメモを取ることは、読書を「内面との対話」として、深い自己理解へ導いてくれるのです。
3. 物語のテーマや問いに注目する
小説には常に「問い」や「教訓」が隠れています。例えば『ウサギとカメ』なら「短期的に力があるものも、コツコツと継続するものには負けてしまう」、『北風と太陽』なら「力づくの解決は必ずしも有効ではないし、逆効果であることもある」という教訓が示されています。
このように寓話であれば「問い」は「教訓」として答えとセットで、かつ明確に描かれています。
しかし、実際の社会ではそうはいきません。1で述べたように世の中には自分とは異なる人しかいません。また社会構造は複雑で、嘘や欺瞞に溢れています。さらに、人は自分自身にも嘘をつき、現実を都合よく捻じ曲げたり、見たくないものから目を逸らします。いわゆるバイアスと言うものです。つまり複雑な自分や社会の中では、そもそも何が問題なのか気づくことすら難しいのです。仮に気がつけたとしてもこの世の中の問題には明確な答えなど存在しないのです。これだけ言うと絶望的ですが、やりようがないわけではありません。
小説というのは、寓話ほどシンプルでなくとも複雑な社会を風刺的に強調して描いていたり、人の中にあるモヤモヤとした違和感に焦点を当てて切り取っていることが多いのです。
小説家とは(皆が皆ではないですが)、そのような違和感に敏感であると同時に、表現に優れている人たちです。彼らが描き出す作品には当然そのよう議論の種、すなわち「問い」をはらんでいるのです。そして物語やキャラクターその「問い」に対する幾つかのアプローチを示してくれます。それらは失敗に終わっているかもしれないし、人や状況を選ぶ方法かもしれません。ただ、先ほども言ったように絶対の答えはありません。ですから当然物語から答えを得ることもできません。しかし、彼らの取り組みから指針や叩き台となるものを汲み取ることはできるのです。
漫然と読書をしていると、面白かった、つまらなかった、で終わってしまえば残るものはありません。しかし、こうした「問い」に意識を向けながら読むと、読書は娯楽を超えて自分自身や社会の「問題」を見つめ直す機会になります。
4. 読後に話し合ったり書いたりする
読んだ後、友人や仲間とその感想や疑問を語り合ったり、SNSや日記にまとめたりすることで、理解がさらに深まります。議論や共有は、ひとりで読むだけでは気づけなかった視点を教えてくれます。
2にも関わる話ですが、「アウトプット」は思考を構造化し、自分の理解を再確認するプロセスです。加えて、人と話すことは新しい視点に触れ、自分の考えとの違いに気がつけます。
この過程は、自分の考えを他人に反響させることで「自分が何をどう感じたか」がより明確になる、すなわち、複雑な個性の集まりの中で、自身がどの座標にいるかのかを測る作業をしているのです。現在の多様化を極めた社会では、孫子の”彼を知り己を知れば百戦殆からず”と言うことは非常に困難です。しかし、物語を読み登場人物の様々な立場をまず自分なりに受け止め、さらに他人にとの意見の交換を経ることで、交錯する人々の認識が色づき一本一本の異なる線として捉えることができるようになります。
まとめ
このように、小説を読むことは「ただ文字を追う」だけでは十分といえません。様々な登場人物の立場に入り、隠れた問いに目を向けて、自分なりの疑問や気づきを積極的に言語化し、共有することで、物語は複雑な世の中を生きる糧となります。こうしたアプローチこそ、誰も教えてくれなかった、本当の読書体験の鍵なのです。
とはいえ、最も大事なことは小説を楽しむ姿勢です。ここに述べたことは、どうにもよるべなく読書というものがわからない、と言う人に向けた足掛かりにすぎません。眼前に広がる物語の大海に身を投じる一助として頭の片隅に入れていただけると幸いです。