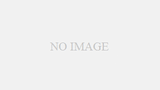さて本日はここ数日のまとめ的なお話です。
今までの記事を見ておくとわかりやすいかもです。
まず、題目のインキュベーション効果とは、ある問題を意識的に考えていない間に、その問題の創造的な解決策や解決方法を思いつく現象のことです。
インキュベーション効果とは
問題解決活動で行き詰まったとき、ひたすら課題に取り組むよりも、一度休憩を取ることで解決に至る可能性が高まることが示されていています。
この「インキュベーション」は、新たな情報と過去の知識との間に内的な関連づけが起こることで、解決のアイデアを生み出すとされています。
これにより、一般的には「難しい問題を解決するには、より多くの努力が必要」と思われがちですが、実は一度手を離すことがブレイクスルーにつながるということがわかります
例えば、寝る前のまどろんでる時や、仕事から離れて散歩している時の方がいいアイデアが思い浮かぶことがあるのは、このインキュベーション効果といえます
ちなみに「incubation」とは、「卵を孵化させる」という意味なんですね。
インキュベーションの三段階
このインキュベーション効果は3つの段階に分けられ(a) プレ・インキュベーション段階、(b) インキュベーション段階、(c) ポスト・インキュベーション段階。
- プレ・インキュベーション段階:問題解決に失敗し、行き詰まる。
- インキュベーション段階:問題から離れ、他の活動をしたり休憩を取ったりする。
- ポスト・インキュベーション段階:休憩後に再び問題に取り組む。
ここまでの話を聞いて思い出すのが先日話したDMNですね。(DMNとは)
DMNと「インキュベーション効果」の関連
• 休憩中や散歩中は注意ネットワークが弱まり、DMN↔︎前頭頭頂制御ネットワーク(FPN/ TPNのひとつ)を行き来するスイッチングが活発になる(これも先日の記事参照)。これが内部思考と課題関連情報の統合を促進し、洞察に至りやすい。
注意・抑制の緩み
• 強いトップダウン制御下では「正解とは無関係」と評価されて弾かれていた遠隔連想が、抑制の低下で意識上に浮上しやすくなり、スプレッディング・アクティベーション(詳しくはこちら)が活発に。
• セマンティック・ネットワーク(こちら)の遠縁ノードが時間とともに活性化し、予期せぬ組み合わせ(創発パターン)を産む。
つまり、インキュベーション効果が起こるのはDMNとTPNの協働があり、その間に、スプレッディング・アクティベーションによってセマンティック・ネットワークが形成されるからなのです。
まとめ
さてこのように、「休息」は「努力」は互いに助け合いをなすという意味で重要だということがわかったと思います。ですが、「休息」と「努力」いずれかが特に大事という話ではありません。
しかしもし、社会が「努力」に傾倒しているならば、「休息」を意識することは「努力」を意識する以上に重要だと言えるでしょう。