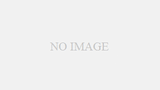他人の身の上話を聞いてると(バカだなあ、なんでそんなことするんだろう)と思って、いざ自分に同じことが降りかかると同じように愚かな対応しかできない。なんてことはありませんか?
これは「ソロモンのパラドックス」といわれ、「他者の問題には賢明な判断ができるのに、自分自身の問題になると適切な判断が難しくなる」という現象のことを指します。このパラドックスの名称は、旧約聖書に登場する知恵者ソロモン王が、他者の問題には的確な助言を与えたにもかかわらず、自分自身の人生では愚かな判断を下したという逸話に由来しています。
今回はソロモンのパラドックスを理解する上で、今まで扱った概念との関連から見てみましょう。
1. 「岡目八目」ともいう
- 岡目八目(おかめはちもく)とは、囲碁に由来する日本語の慣用句で、「第三者のほうが当事者よりも状況を客観的に把握でき、より的確な判断が可能である」ことを示しています。
- ソロモンのパラドックスは、この岡目八目という現象とほぼ同じメカニズムによって生じます。すなわち、自分自身が当事者であると、感情や欲求がワーキングメモリを占有し、判断材料の整理が難しくなり、適切な判断が難しくなります。しかし、第三者として他人の状況を観察すると、余計な感情情報が少ないぶんワーキングメモリの容量に余裕が生まれ、論理的に状況を分析できるのです。
- 囲碁や将棋で解説者がいい読みができるのはこのことですね(しかし昨今は藤井聡太先生など解説者泣かせの棋士も多いですが)
2. 「インキュベーション効果」との関連
- インキュベーション効果とは、先日解説した通り問題をいったん脇に置き休憩すると、無意識下で情報が再編成され、再び向き合うと洞察が得やすくなる現象です。
- 休憩中は関連刺激が少なくなるため、ワーキングメモリの負荷が低下し、記憶の再結合や新しい連想が進みやすくなります。結果として、問題を再検討する際にはより客観的な視点が得られ、ソロモンのパラドックスが緩和されます。
3. 「デフォルトモードネットワーク(DMN)」との関連
- デフォルトモードネットワーク(DMN)とは、人が意識的に課題に集中していないとき、ぼんやりと物思いにふけったり自分自身や他者の心情について考えたりする際に活性化する脳のネットワークです。
- 当事者として悩みを抱え込むと DMN が過剰に活性化し、ネガティブな反芻思考がワーキングメモリを圧迫します。その結果、必要な情報を同時に保持・操作する能力が低下してしまい、冷静な意思決定が難しくなります。
- 一方、自分自身の問題を一時的に忘れて別の活動を行ったり(インキュベーション効果)、他者視点で考えたりすることで、この過剰なDMNの活性化を抑え、ワーキングメモリの領域を回復させる働きをします。そうすることで問題に対して冷静かつ客観的な判断をすることが可能になると考えられます。
まとめ
以上のように、ソロモンのパラドックスは他者視点の重要性を示し、問題から一時的に距離を取ることで思考が整理される現象を反映しています。これらを統合することで、より深く人間の認知や思考パターンについて理解することができそうです。
またこのようなソロモンのパラドックスのような現象を避けるためにノートに書き出したり、人に相談するのですね。カウンセリングやコンサルタントの役割もソロモンのパラドックスによるバイアスを抜け出すという効果も大きいでしょう。